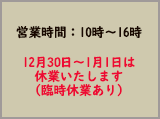益子焼は、嘉永6年(1853)大塚啓三郎が窯を築いたのが始まりといわれている。啓三郎は茂木の福手村に生まれたが、少年時代笠間の宝田院慈眼寺において寺子屋教育を受けたときに笠間焼の久野窯で技術を習得した。
その後益子村の大塚家に婿養子に入って農業に従事していたが、実家に帰る途中の益子村字大津沢で良質な陶土を発見したのをきっかけに、根古屋に窯を築き農閑期に 焼き物を始めるようになった。

安政2年(1855)には黒羽藩から三田称平が郷奉行として赴任すると、藩の財政を 潤そうとし益子焼を保護奨励した。
安政4年(1857)年になると、5つの窯元に対して黒羽藩より奨励覚書が交付され財政的な援助を得、 江戸にも出荷されるようになった。
明治4年(1871)の廃藩置県により黒羽藩は解消し、益子焼は御用窯から民窯へと移行した。
藩からの援助は無くなったものの、創業から20年近く経過して窯数も増加し、しかも東京という大きな消費地を控えていたので業績は着々と伸び、また関東近県にも販路が広がっていった。

しかし、明治末頃になると生産過剰と粗製乱造によって徐々に売れ行きが悪くなっていった。
また最大の消費地であった東京の生活が、ガスの普及に伴い軽金属の鍋・釜へと移行していったこともそれに拍車をかけた。
大正時代になると世の中の不景気とも重なり、生産を一時中止する窯元が続出した。
そうした中に起きた大正12年(1923)の関東大震災によって東京での日用品不足という事態を招いたことが、逆に益子焼需要の急増につながり、いくら作っても間に合わないほどの好況をもたらした。
しかしそれも一時的なものにすぎなかった。

大正13年(1924)になると濱田庄司が東京に近いのに純粋な土地柄にひかれ益子に移住し、柳宗悦らと共に用の美を唱えた民芸運動を推めた。
また佐久間藤太郎などの地元陶工たちに大きな影響を与え、益子焼は少しずつ芸術品としての側面も持つようになった。
戦前戦中を通しても、芸術品よりも以前と同じような台所用品を中心に生産され、物資不足になると金属の代用品としての生産も行われた。窯元の数は、明治20年代から終戦の頃までは多少の浮き沈みはあるが、ほぼ50軒程度で推移していた。
戦後は世の中が復興するに従い生活様式が変化し、従来の台所用品の需要は大幅に減少、生産も縮小していった。
しかし昭和30年(1955)濱田庄司が人間国宝に認定されると民芸品としての益子焼が再び注目され、昭和41年(1966)に益子焼窯元共販センターがオープンすると陶器市が開かれ多くの人が訪れるようになった。
昭和52年(1977)には濱田庄司邸の一部が益子参考館としてオープンし、国内外からの収集品などが一般公開されるようになった。

- 濱田庄司邸 撮影 佐野昌弘 氏(1978年撮影)
この間、町外からも陶芸を志す若者も増え、特に高村光太郎賞など有力な賞を
次々に受賞した 加守田章二(かもだしょうじ)などの逸材を輩出した。
平成5年には焼き物を展示した美術館として陶芸メッセ・益子がオープンし、
平成8年には島岡達三が入間国宝に認定された。